2012年11月19日
航空医療学会 後編
はいさい。フライトドクター ヨシバードです。
第19回を迎えたこの学会は、ドクターヘリが全国に徐々に普及していることもあり、回を追うごとに参加人数が増えています。

今年のテーマは「Total prehospital timeを考える」でした。
ドクターヘリの最大の強みは、もちろん搬送時間の短縮もありますが、治療を大幅に前倒しできることにあります。
「いかに患者接触までの時間を短くするか」
多くの施設がアイデアを出し合いました。消防へ救急コールが入った時点でドクターヘリも要請するキーワード方式を取り入れている病院も広がりつつあります。交通事故の種類から自動で「高エネルギー」と考えられるものを病院に自動送信するシステムの開発も斬新でした。
病院前処置をどこまでするのか、どこで行うのかも議論の焦点となりました。中でも、救急隊の徹底的な教育により、医師接触前の診察と処置を確実に行ってもらい、引継後は同じことをすることなく次の医療処置から開始するという但馬ドクターヘリの発表は心に残りました。お互いのスキルと能力を信頼できる関係であってのことです。
沖縄県では消防間の温度差がまだまだあります。少しでも縮めることができるようなプログラムを早急に作る必要があります。
もう一つのビックテーマは「基地の紹介」でした。2001年に第一機が岡山で運航開始してから、今年で11年。ドクターヘリ特別措置法を追い風に、現在全国33道府県39機まで増えています。南から北まで2000km以上もある本邦は、農村部、都市部、山岳地帯、積雪地帯などなど、実に様々なドクターヘリが存在します。輸血を持ち出すというドクターヘリには驚きました。装備も機材も独自の進化を遂げていて、ユニークなロゴもあり「ご当地ヘリ自慢大会」さながらで興味深かったです。

一番心に残ったのは、福島県ドクターヘリでしょうか。原発事故という他県にはないハンデを背負いながらも、いかに飛行禁止区域の近くにヘリを降ろし、不慮の事故から原発作業員を守るか苦慮している様子が伝わりました。
沖縄県ドクターヘリは、Hナースが全国でも数少ない基地発進方式の強みと弱み、そして離島を多くかかえる海洋県ならではの工夫について発表をしてくれました。ポスターが色鮮やかな熱帯カラー(?)もこだわりの一つです。

ひーじゃーセンター長も沖縄県ドクターヘリ搬送症例の予後調査の発表を行いました。
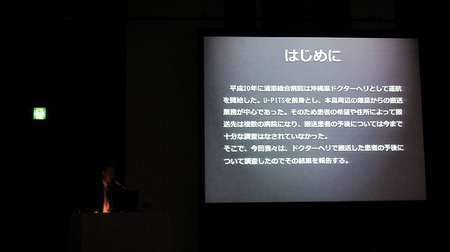
今後も、全国の仲間たちと共有しあい刺激を受けながら、沖縄県ドクターヘリを盛り上げていこうと思います。
第19回を迎えたこの学会は、ドクターヘリが全国に徐々に普及していることもあり、回を追うごとに参加人数が増えています。

今年のテーマは「Total prehospital timeを考える」でした。
ドクターヘリの最大の強みは、もちろん搬送時間の短縮もありますが、治療を大幅に前倒しできることにあります。
「いかに患者接触までの時間を短くするか」
多くの施設がアイデアを出し合いました。消防へ救急コールが入った時点でドクターヘリも要請するキーワード方式を取り入れている病院も広がりつつあります。交通事故の種類から自動で「高エネルギー」と考えられるものを病院に自動送信するシステムの開発も斬新でした。
病院前処置をどこまでするのか、どこで行うのかも議論の焦点となりました。中でも、救急隊の徹底的な教育により、医師接触前の診察と処置を確実に行ってもらい、引継後は同じことをすることなく次の医療処置から開始するという但馬ドクターヘリの発表は心に残りました。お互いのスキルと能力を信頼できる関係であってのことです。
沖縄県では消防間の温度差がまだまだあります。少しでも縮めることができるようなプログラムを早急に作る必要があります。
もう一つのビックテーマは「基地の紹介」でした。2001年に第一機が岡山で運航開始してから、今年で11年。ドクターヘリ特別措置法を追い風に、現在全国33道府県39機まで増えています。南から北まで2000km以上もある本邦は、農村部、都市部、山岳地帯、積雪地帯などなど、実に様々なドクターヘリが存在します。輸血を持ち出すというドクターヘリには驚きました。装備も機材も独自の進化を遂げていて、ユニークなロゴもあり「ご当地ヘリ自慢大会」さながらで興味深かったです。

一番心に残ったのは、福島県ドクターヘリでしょうか。原発事故という他県にはないハンデを背負いながらも、いかに飛行禁止区域の近くにヘリを降ろし、不慮の事故から原発作業員を守るか苦慮している様子が伝わりました。
沖縄県ドクターヘリは、Hナースが全国でも数少ない基地発進方式の強みと弱み、そして離島を多くかかえる海洋県ならではの工夫について発表をしてくれました。ポスターが色鮮やかな熱帯カラー(?)もこだわりの一つです。

ひーじゃーセンター長も沖縄県ドクターヘリ搬送症例の予後調査の発表を行いました。
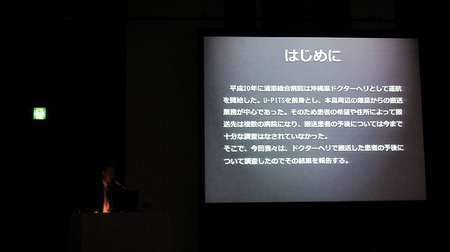
今後も、全国の仲間たちと共有しあい刺激を受けながら、沖縄県ドクターヘリを盛り上げていこうと思います。
Posted by ドクターヘリオキナワ1 at 11:21│Comments(0)









